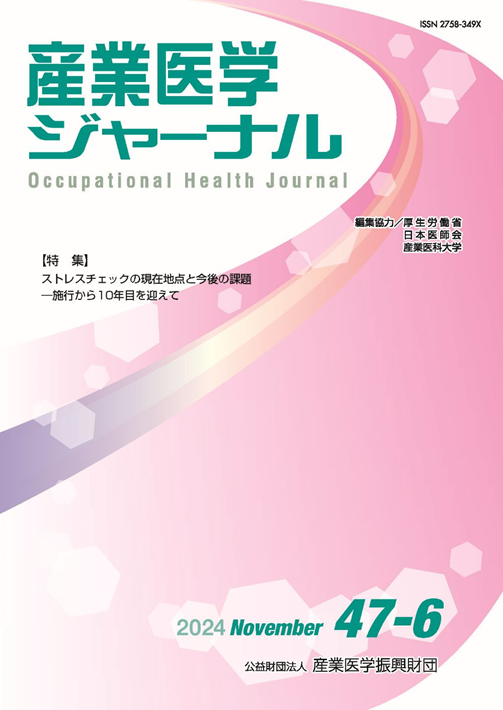橋本晴男JAWHO理事は、「産業医学ジャーナル」誌(発行:(公財)産業医学振興財団)2024年11月1日号に、能登半島地震の避難所の環境調査と対策などに関する記事を寄稿しました。
■ タイトル: 平時の産業保健活動の、災害被災地における保健予防医療活動への展開:能登半島地震支援
■ 著者(敬称略):武藤剛(主著者、北里大学)、橋本晴男(共著者、JAWHO)、中村裕之(共著者、金沢大学)、他
■ 記事へのリンク
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfjrnl/47/6/47_73/_article/-char/ja
■ 内容(要旨):
2024年1月に発生した能登半島地震では約1万人以上の被災者の方が公民館等での避難生活を余儀なくされました。金沢大学は石川県羽咋郡志賀町で避難住民への医療支援を継続的に実施しており、これにJAWHO、北里大学、松本大学が参加して、避難所の空気環境に関して調査を行いました。
2024年7月の志賀町の避難所での調査では、避難室(計10室)の使用状況、換気量などを基に、「換気シミュレーター(日本産業衛生学会)」を利用し、室内のCO2濃度を推定しました。この結果、換気装置を止めていたと考えられる夜間での CO2濃度は平均2,309ppmで、基準値の1,000ppmよりかなり高く、空気環境は悪かったと推定されました。実際に発生した COVID-19やインフルエンザ等の原因の一つとなった可能性があります。また、避難室に空気清浄機を設置したと仮定した場合には、環境が良化すると推定されました。
また、避難した住民の方への質問紙調査の結果では、室内の不快な臭い(生活臭)(回答中の19%)や、埃っぽさ(同19%)を感じる方が多くおられました。一方、指定避難所7カ所の管理者 に尋ねたところ、室内環境の課題での優先度は、①感染症、②水の衛生(トイレ、シャワー)、③臭い(トイレ、生活臭)、の順でした。
以上から、避難所の空気環境の改善対策として空気清浄機の活用が有効と考えられました。災害直後にすぐ使えるよう、避難所になりうる公的施設(公民館、学校等)に平時から空気清浄機を導入しておくことは、今後の自然災害への備えとして有力な選択肢と考えられます。
(注:上記の空気環境の調査と対策の詳細については、本ニュース、2024年12月07日付け、「橋本理事が第21回日本予防医学会学術総会で発表」をご覧ください。)